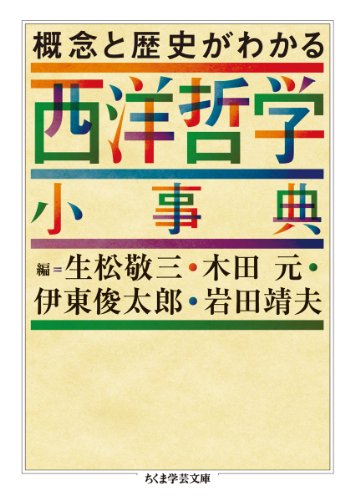【1841冊目】アンリ・ベルクソン『精神のエネルギー』
実は、最初は『時間と自由』を読んだのだが、まったく歯が立たなかった。哲学書はずいぶん久しぶりだったが、やっぱり難しい。
そこでいったん回り道して、『西洋哲学小辞典』でアウトラインをつかみ(これはこれで、わかったようなわからないような説明だったが)、篠原資明『ベルクソン』を読んで外堀を埋め、「ベルクソンによるベルクソン入門」と謳ってあった本書に進んだ……のだが、実は本書が一番わかりやすかったというオチが。いや、篠原氏の本も良かったのだが。
講演録4篇とエッセイ3篇を集めた一冊。特に4つの講演録は、さすがの分かりやすさと展開の巧さが光る。
まず、最初の講演録〈意識と生命〉の中の、過去と未来に関する説明が興味深い。私たちは、「過去」を記憶して「未来」を予期することはできるが、では「現在」はどうなのか。現在を瞬間と考えれば、人はそれを意識することはできない。「今を生きる」と言われても、そもそも「今」なんて人間には捉えきれないじゃないかと、以前悩んだことを思い出す。
ベルクソンは「過去」と「未来」の間を「持続」として捉えた。人は過去に寄りかかりつつ、未来に身を傾けている。その間を架橋しているのが「意識」なのだというのである。
だが、私たちはすべての過去を常に想起しているわけではない。続く〈心と体〉での説明によれば、過去の全体は意識下にあって、脳はそこから「行動に有用なもの」を選んで意識のもとに置くのだと解説されている。このくだりからは、ベルクソンが精神と脳の関係をどう考えているかがよくわかる。ベルクソンは「脳=精神」という考え方を批判する。脳は決して精神そのものではなく、精神の働きを枠づけ、表現し、精神が適応すべき外的状況を身ぶりであらわす「パントマイムの器官」なのである。
この「意識と記憶」に関連してちょっと面白いのが「既視感」(デジャ・ヴュ)に関する考察だ(〈現在の記憶と誤った再認〉)。今まさに体験していることなのに、それをすでに見て知っている、と感じるアレである。それは現在の体験であるにも関わらず、間違いなく記憶の中にあることなのだ。
論証の過程をすっとばしてベルクソンの結論だけを言うと、ここでの記憶とは「現在の記憶」なのである、とベルクソンは言うのである。実は私たちは「現在」を知覚するとともに「記憶」している。だがそのことは、普段は意識に隠れたままになっている。それが顕在化した結果、現在であるにもかかわらず記憶の中の出来事として感じられるという「既視感」が出現するというのである。
興味深いのは、ベルクソンがこれに、もうひとつの「よくある現象」を重ねて論じていることだ。それは、見慣れた言葉であるにも関わらず、その語が「新しい語」に見えるというあの現象である。アルファベットでもそういうことがあるというのは意外だったが、私も時々、ある言葉がどうしても別の「無意味な記号」に見えてしまって困ることがある。例えば「言」という文字を何度も見たり、書いたりしているうちに、なんだかそれだけが奇妙な図形に見えてくる、というようなケースである。
なぜこうしたことが起きるのか。ベルクソンによれば、文章を読む際、私たちは一つ一つの単語を追っているのではなく、全体の意味を仮説的に作りなおしながら、いわば文章の少し先に軸足を置いている。
「現在はそれ自体においてとらえられるのではなく、それが侵入していく未来の中で見られている。こうした躍動(エラン)がすべての心理状態を突き抜けてまたぎ越し、そこに特殊な様相を与えているのだが、しかしそれはつねにそうであるために私たちはそれに慣れてしまい、それがあることよりもそれが欠けてなくなったときにのみそれと気付く」(p.209-210)
ここに「躍動」(エラン)という言葉が出てきた。実は既視感のくだりでも「現在の記憶は意識の躍動の弱まりや停止をまってあらわれる」という指摘がなされている。言い換えれば、普段は「意識の躍動」があるからこそ、既視感や「見慣れた言葉の変容」が起きずに済んでいるということである。
では「意識の躍動」とは何なのか……ということなのだが、これについては、やや長くなったのでまたいずれ。今回はわずかにベルクソン哲学の上澄みを舐めた程度に終ってしまったが、今後もこのヒトとは良いお付き合いができそうだ。